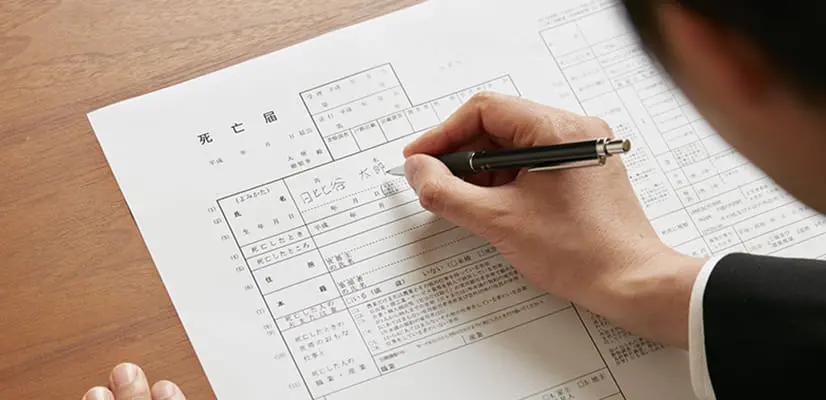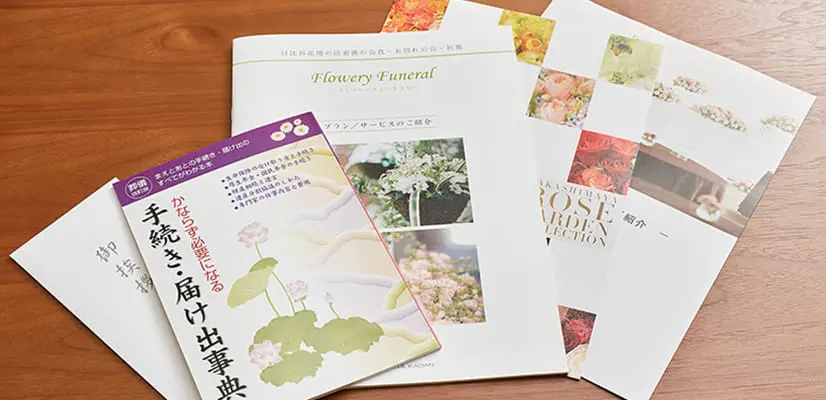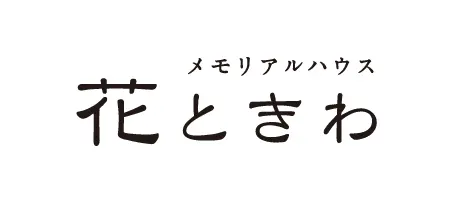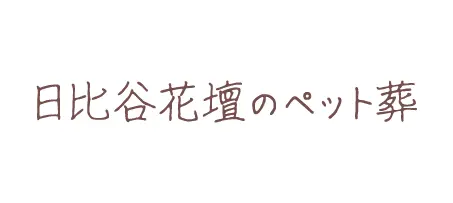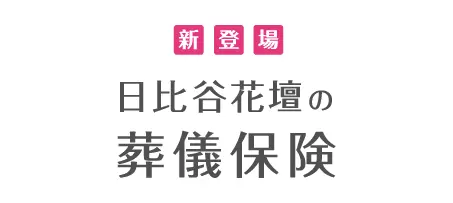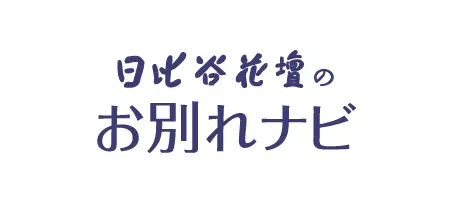喪服とは何か:基本マナー・購入方法や着るタイミングについて

- 葬儀法要に参列するときのマナー
- 身だしなみ・服装

目次
喪服とはどんな服?購入場所は?
喪服とは、一般的にはツヤのない素材でできた黒い洋服のことを言います。黒いスーツとは若干異なる素材でできているため、万が一に備えて一着用意しておいて間違いのない服です。
スーツなどを取り扱っている洋服店などで購入できます。長く使うことになるので、安価過ぎないものを一着用意しておくとよいです。
個人または葬儀社を通してレンタルすることも可能です。どうしても用意ができない場合、急なことで購入する時間がなかったときなどはレンタルを利用します。
喪服には本来、
・正喪服
・準喪服
・略喪服
とランクがあるともいわれています。
正喪服は男性の洋服の場合モーニング、女性の洋服の場合はアンサンブル、和服の場合は五つの紋付黒喪服と言われています。2~3等身までの遺族が着用し、血縁関係のない参列者や遠い親族は着用しません。
準喪服はパンツの場合はブラックスーツに黒いネクタイ、レディーススカートの場合はワンピースやスーツスカート、レディースパンツの場合は黒いスーツに黒いインナーです。
略喪服は急な弔問や通夜、法要などで着用します。ダークカラーの洋服で、フォーマルでないものを着用します。
遺族のランクより高い喪服を着てはいけない、というようなマナーも存在しますが、モーニングや五つの紋付を着用している人を見かける方が珍しくなっています。あまり気にしすぎず、遺族だったとしてもいわゆる「準喪服」で参列して問題ありません。
髪型については、あまり派手すぎない髪色と髪型がよいとされています。
ダークブラウン程度であれば無理に黒染めなどをする必要はありません。特徴的な髪の色がトレードマークなのであればそのまま参列しても問題ないでしょう。ご遺族との関係もありますし、何か言われるのが不安であるならばスプレーなどで黒染めするのが無難です。
大切なことはどんな服を着るかというより、どんな服で最後に故人さまと対面したいかということです。しきたりや習慣にとらわれすぎず、式を邪魔しないでいかに自分の気持ちを伝えられるかを大切にしてください。とはいえ、周りの目は気になるものです。喪服に限らず、葬儀に関する文化は地域によって大きく異なり、正解や不正解はありません。心配な場合は、葬儀社やご遺族にご確認ください。
女性の喪服(レディーススカート・レディースパンツ)
スカートを着用する場合は、つやのないブラックのワンピース・アンサンブルを着用します。いわゆるブラックスーツだと光沢があり、喪服とは違うものになるので注意が必要です。
レディースのパンツスーツの着用も問題ありません。
たしかに、考え方によってはパンツスーツはスカートに比べ「格下」にあたりますが、だからと言って失礼に当たるわけではありません。普段の考え方や恰好、スタイルによってパンツを選ぶことに全く問題はありません。また、高齢者や寒冷地域では動きやすさと体調を優先してパンツスタイルが好まれることもあります。
夏は半袖を着用しても問題ありません。境内や墓地は高温になりやすく熱中症の危険があるので、過ごしやすい服装を選びます。
冬には式場までコートを着ていっても問題ありません。できるだけダークカラーを選び、受付で脱ぎます。あたたかい下着なども着用し、体調を崩さないように気を付けてください。
アクセサリーや靴、ネイルについては以下の項目「喪服に合わせる小物:靴・ネクタイ・アクセサリーなど」をお読みください。
冬や雨の日、夏の喪服についてはこちらの記事もご覧ください。
冬の葬儀に着るコートと靴の選び方|オハナクラブ>>
雨の日の葬儀の服装|オハナクラブ>>
夏の葬儀の服装はどうするべき?|オハナクラブ>>
男性の喪服(メンズスーツ)
メンズスーツは光沢のないブラックフォーマルスーツが喪服として販売されています。
前述したようにモーニングは正喪服と言われ、着用しても問題ありません。
一般的にスーツ専門店などで「喪服」として販売されているのはダブルかシングルのブラックフォーマルです。スリーピースはツーピースより格上と見られることがあるので、参列する場合は避けたほうがよいとされています。
シャツは白を着用します。
夏でも基本的には白いシャツにブラックスーツを着用し、ポロシャツや半袖のワイシャツでの参列は失礼に当たります。また、ネクタイも着用します。葬儀場は空調が効いて涼しいところもありますが、墓地や寺の本堂などは高温になることもあります。体調には十分気を付けて、必要があれば脱いで体温を調整してください。
靴やかばん、ネクタイについては以下の項目「喪服に合わせる小物:靴・ネクタイ・アクセサリーなど」をお読みください。
冬や雨の日、夏の喪服についてはこちらの記事もご覧ください。
冬の葬儀に着るコートと靴の選び方|オハナクラブ>>
雨の日の葬儀の服装|オハナクラブ>>
夏の葬儀の服装はどうするべき?|オハナクラブ>>
喪服に合わせる小物:靴・ネクタイ・かばん・アクセサリー・ネイル
どのような小物にしても、華美に見えるものはNGとされています。
キラキラ光って見えるボタンなどがついているものや、金具の大きい小物は避け、できるだけ光沢のないものを選びます。また、動かすと音が鳴ってしまうものにも注意が必要です。
■アクセサリー
指輪は結婚指輪以外は着用しません。
耳飾りに関しては、一粒の真珠までがよいとされています。ぶらさがって揺れるタイプのピアスやイヤリングは避けます。
首飾りは一般的に真珠のものがよいとされ、そのほかのものは避けます。
■靴
ヒールの高すぎないパンプスか革靴を選びます。色は黒で、あまり光沢のないものを選びます。
仏教の葬儀では殺生を連想させるものを使用することを避けますので、ワニ革やヘビ革とわかるものは避けます。ちなみに、同じ理由でファーの着用も好ましくないとされています。
雨が降った時には長靴など雨雪に対応したものを履いてもかまいません。
■かばん
大きなボタンや華美に見える大きな金具がついているものは避けます。つやのない黒い素材のものを選びます。また、仏教式の葬儀では殺生を連想させるものは避けるので、動物革のものも避けます。参列者と隣り合って着席したり、焼香や献花のために動いたりするので、荷物は小さくまとめておくとよいです。どうしても大きな荷物を持ってくる必要がある場合は受付に預けたり駅のコインロッカーなどを利用したりします。
■ネクタイ
光沢のない黒い無地のものを選びます。とても安価に手に入れることのできる品ですが、あまり安価すぎると見た目にわかってしまうので注意が必要です。柄はないものが好ましく、柄があったとしても目立たない織柄くらいがよいとされています。ネクタイピンも付けずに参列します。
■ネイル
あまり派手すぎるものは避けます。ご自宅でオフできるものはネイルオフし、どうしてもネイルをする必要がある場合は目立たない色(ベージュや薄いピンク)のマニキュアを使用します。急なことでオフできない場合は、黒いレースの手袋などを着用することもできます。髪の色と同じで、何か言われるのが気にならない、故人に最後に爪を見せたいという時に、無理に外す必要はありません。
子どもの喪服
■赤ちゃんの喪服
派手な色や華美な装飾がついていないものであれば何でも大丈夫です。
また乳児の参列についても問題はありませんが、すぐに身動きが取れないことが多いのが葬儀です。
特に親族でない場合は喪主に確認の上、準備を整えて参列します。参列しない、というのも一つの手です。葬儀の参列だけが弔いの方法ではありません。
赤ちゃんの喪服についてはこちらもご覧ください。
赤ちゃんの喪服マナー、参列する時のマナー>>
■子どもの喪服
小学校以上で制服があるのであれば、制服を着用します。
制服は正装にあたりますから、葬儀で着用しても失礼には当たりません。
制服がない場合は、落ち着いた色味で華美な装飾のない服を選びます。
基本的には白いシャツに黒や紺などのボトムスです。
衣料店には子ども用の喪服も用意されていますが、子どものはやい成長にあわせて無理して喪服を買いそろえる必要はありません。
詳しくはこちらの記事もご覧ください。
子供の喪服の代用、参列する時のマナー>>
喪服を着るのはいつ?
■通夜
通夜は基本的に平服で参列します。仕事に行くスーツや作業着で参列しても失礼には当たりません。むしろ喪服を着ていくと「不幸を予想していた」としてかえって失礼だという考え方もあります。
ただし、近年は喪服での参列も増えています。逝去から通夜・葬儀までの日程がひらき、余裕のある案内がされていることが一つの原因です。
厳格なルールはありませんので、心配であれば、ダークカラーのスーツなどを着用します。
■葬儀
指定がない限りは喪服で参列します。
■直葬
指定がない限りは喪服で参列します。
とても近しい人で行うお葬式のスタイルですので、ご家族で話し合って決めても問題ありません。ただし、火葬場ではほかの家のご遺族とも鉢合わせることがあるのでその点を留意します。
■お別れの会、社葬:喪服、平服
服装の指定がある場合が多いです。
平服と指定があった場合は、落ち着いたトーンの服を選びます。
平服については詳しくはこちらをご覧ください。
お別れの会の服装-平服でお越しくださいってなに?>>
■法事
三回忌(亡くなって2年の法要)までは喪服もしくは準喪服を着用すると言われています。参列者は喪主より格の高い喪服を着用しないようにするため、準喪服を着用します。七回忌以降は喪主・参列者ともに略礼服もしくは平服で問題ありません。
近年は法要の参加者を近しい親族のみにし、小さく行うことも増えています。一周忌から平服を指定することも多々あります。心配な時は喪主に確認をします。
日比谷花壇のお葬式は日比谷花壇が運営する葬儀のトータルサービスです
日比谷花壇のお葬式は、創業150年を超える花屋の日比谷花壇が、
長い歴史の中で培われた技術とホスピタリティをいかしてお手伝いする葬儀サービスです。
通常の葬儀社と同じように、病院等へのお迎えから、当日の施工、アフターサービスまで日比谷花壇が一貫してお手伝い。
くわしくはこちらをご覧ください。
日比谷花壇のお葬式とは|日比谷花壇のお葬式>>
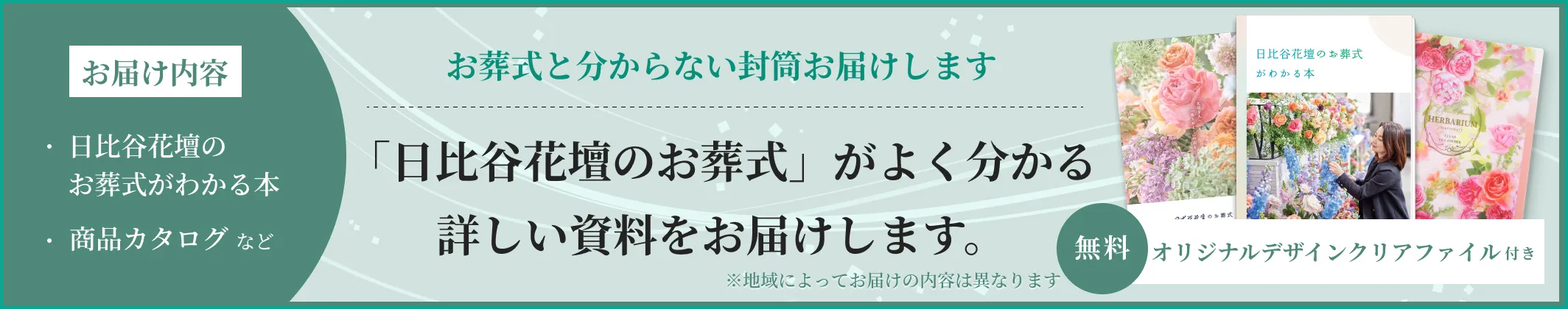

会員制度:オハナクラブ もございます
日比谷花壇のお葬式の会員制度「オハナクラブ」は、入会費・年会費無料のサービスです。
葬儀のマナーやお花の知識、葬儀の準備や終活に役立つ情報をお届けしています。
詳しくはこちらをご覧ください。
オハナクラブについて|日比谷花壇のお葬式>>
関連記事
-

- 葬儀法要に参列するときのマナー
- 会葬・参列
お通夜とはなにか?流れや服装・マナー、参列する時の持ち物について解説
-

- 葬儀法要に参列するときのマナー
- 会葬・参列
お葬式はどこまで参列する?
家族葬・一般葬など形式ごとの参列範囲の解説 -

- 葬儀法要に参列するときのマナー
- 身だしなみ・服装
喪服とは何か:基本マナー・購入方法や着るタイミングについて
-

- 葬儀法要に参列するときのマナー
- 年忌法要 お盆
「月命日」とはなにか?いつまでどんなことをすればいい?
-

- 葬儀法要に参列するときのマナー
- お布施・香典作法
香典とは何か-いまさら聞けない葬儀のギモン
-

- 葬儀法要に参列するときのマナー
- 身だしなみ・服装
著名人のお別れの会-参列方法や服装について
いつでも、どんなことでもお問い合わせください
0120-こちら 土日祝・深夜・早朝 24時間365日 事前相談 資料請求・
見積依頼